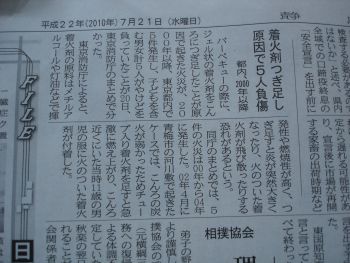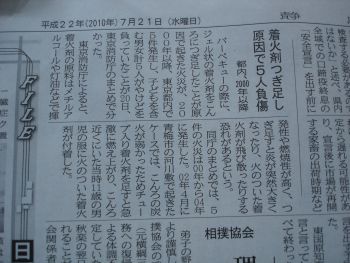
静岡新聞 平成22年7月21日
バーベーキューの祭、ジェル状着火剤をこんろにつぎ足したことが
原因で負傷した人が、都内だけで2000年以降5人もいた。 という。
(東京消防庁調べ)
今は簡単に(自動的に)火がついたり、IHのように火を使かわなかったり
の生活が多くなってしまったが、人類の歴史からみれば、
火おこし は
当たり前で大変なことであった。
自分の経験から思うのだが、人は幼児期に火に興味を持つと思う。
本能かも知れない。
小さい頃、
炭を粉にし、火鉢の上でその粉をバラバラと落すと、炭火の上で
粉は線香花火のようになった。 ある意味幻想的であり、おもしろかった。
また、ある冬のこと、幼稚園のころだったか、
北風を防ぐための、稲藁を組んで垂直の風よけの塀のようなものが昔はよくあった。
この藁にマッチで火をつけて遊んだ。燃えては炭なりおもしろかったのだ。
たが、つづけていると火が大きくなり、どうにもならなくなった、バケツで水を
運ぶも、子供のこと自分が水をかぶってしまう始末。
あやうく、住居が火事になるところだったが、家人が気づき難を逃れた。
藁の塀は大半が燃えてしまった。
こんな経験を持つ。
人類の特徴、
直立歩行、 道具をつくること、
火を使うこと
火は人類しか扱えない。
火は人類にとって大事なことである。
バーベキューやキャンプの際などに、 子供たちに、よくよく火については
教えてあげないと いけない。
そして、それは子供たちが自分で自分の身を守ることにつながるのだから 。
 環境| 浜松市|
環境| 浜松市|